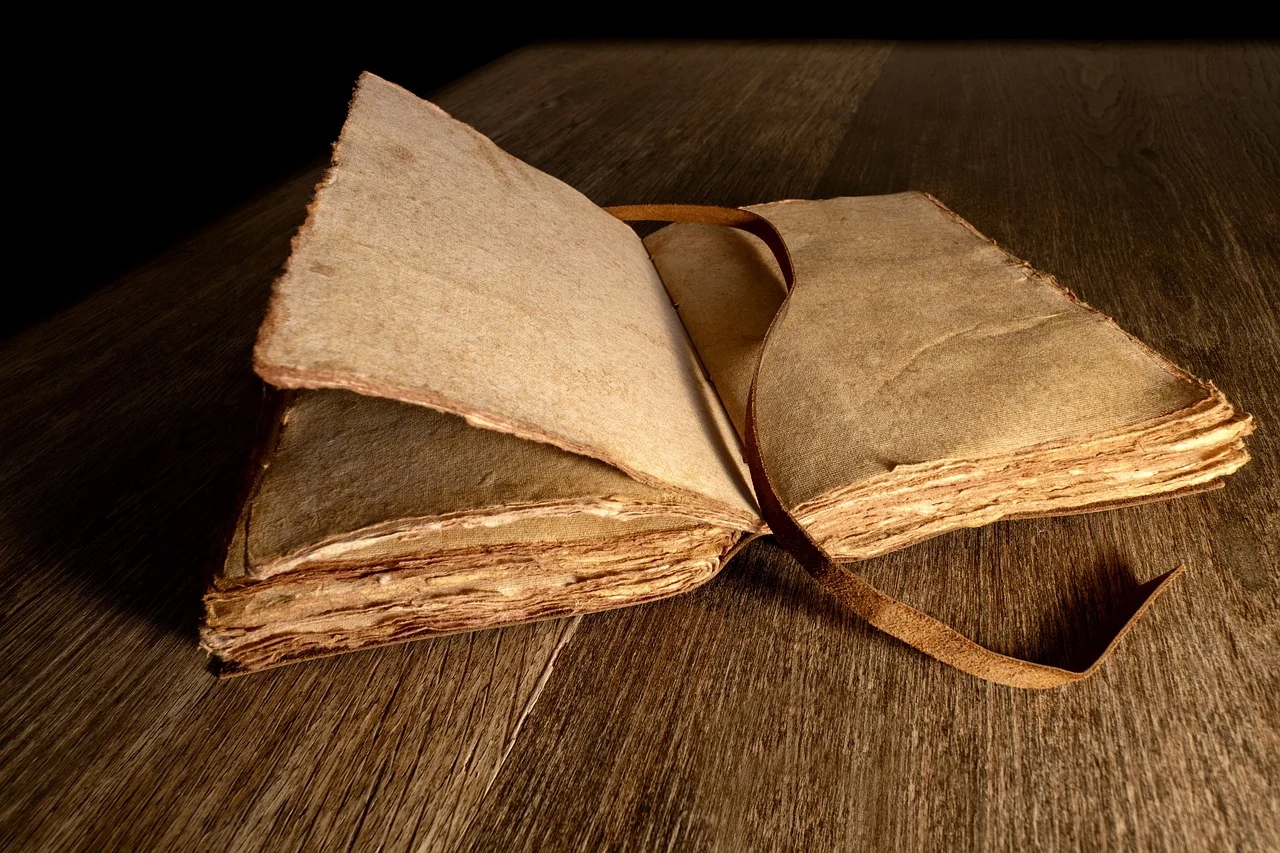私がまだ学生の頃、母が言っていた言葉を最近たまに思い出す。
「フィクション作品くらいはハッピーエンドでいて欲しい」
当時の私は、でもそういう作品の大半ってご都合主義的で無理やりハッピーエンドにしてない?現実にそんなこと起こりっこないのに。なんて思っていたんですが。
最近、母の真意はわからないけれど、自分もハッピーエンドな作品を求めるようになってきたというか、あまりに救いがなかったりモヤモヤ感が残る作品を受け入れられなくなってきているかもしれない、とぼんやり感じるようになってきました。
それだけ私も歳を取ったということだ、と考えても良いのかもしれません。
たとえば学生の頃の私が好きだったのは映画『リリイ・シュシュのすべて』だったり、漫画なら山岸涼子さんの『日出処の天子』や池田理代子さんの『オルフェウスの窓』だったりと、わかる人はわかると思うけれど救いがないと言ってもいい作品が多い。
壁井ユカコさんの『キーリ』シリーズや『No Call No Life』のように心がひりつくような作品や、真梨幸子さんの『殺人鬼フジコの衝動』のようないわゆるイヤミス作品も好きでしたね。
ちなみに『日出処の天子』や『オルフェウスの窓』などは私は現役世代ではなく、母がやはり学生の頃自身の実家で集めていた→結婚後に自分で文庫版を買い直して家に置いておいた、というパターンで私が読むに至っています。
ただ、あんなに大好きだった作品たちも、年々通読しようとすると特に精神面の疲労がすごいな、というのを二十代半ば頃から感じてはいたんですよね。そしてここ何年も読み返せていない。
代わりに、たとえば佐々木倫子さんの『動物のお医者さん』だったり魔夜峰央さんの『パタリロ』だったり、あるいは川原泉さんの著作だったりと、もう少し軽やかに楽しめる作品の方を手に取る機会が増えてきている。
同じようにイヤミス分類されている(?)湊かなえさんの『告白』のように、後味は悪いけれど一応犯人には何らかの制裁が加えられているような作品を好むようになる、など。
肉体面にも体力の衰えがあるように、精神面でもそういう衰えというのがあるのかもしれない、と思わざるを得ないわけです。
それと同時に、新しい作品に接するときに、ネタバレを踏んでから大丈夫そうであれば観たり読んだりする、ということも年々増えてきました。
昔も別にネタバレ絶対ダメ!派ではなかったんですが、あえて自分で踏みに行くことが格段に増えたといいますか。
ハッピーエンドとまではいかなくても理不尽が理不尽なままで終わらない、いわゆるスカッとジャパン的な要素があるか。
誰も彼も救われないまま終わるなら、私の苦手な要素はなさそうか(一例を挙げると人間のエゴのせいで動物が死んじゃうとか)。
心の準備をきちんとしておかずに苦手な要素(いわゆる自分にとっての地雷表現)に触れてしまうと最近は気分が著しく悪くなってしまって視聴・読書を継続できないので、どうしてもワンクッション必要になってきてしまっているのだ。
自分の意図しない形・タイミングで自身の感情を強く揺さぶられると疲れてしまうので出来ればそういう事態は避けたい、という防衛本能のようなものだと考えても良いかもしれません。
もちろん、ネタバレなんてしないで欲しい、記憶も知識もまっさらのまま、自作に触れて欲しいと思っている作り手さんもいることは承知しているんですけれどね。
これに関してはもう自分の心の強度(一度鬱による休職も経験しているのでその時点から強度が下がっている可能性もある)なのか、純粋に加齢によるものなのかはわからないけれど、学生の頃のような感性はもう戻ってこないんだなぁ、失われたんだなぁと少し寂しくも思ったりします。
なお、アンハッピーエンドが好きだからといって、個別具体的な作品名は伏せますが、病気や死が頻繁に登場した00年代携帯小説や、空港で彼女が倒れて助けてください!って叫んでいたあの作品は、お涙頂戴ありきで病気を作品で扱ってやしないかと思って当時から苦手でした。
この感覚は、たとえば24時間テレビが障がい・難病を抱えている方を「使って」(あえてこの表現にする)感動しろと押し付けられていると感じて批判したくなるのと近しい感覚かもしれません。
特に空港でのシーンが印象的な後者の作品に関しては、テレビドラマ版で男女主人公を演じていた2人による別作品『白夜行』の方が個人的にはとても好みでした。
と、だいぶまとまりのない文章になってしまいましたが、とりあえず人生のうちにあと何度、学生の頃好きだったと挙げた作品たちを読んだり観たりし直す機会があるか、気力体力面を含めてわからないので、1日でも若いうちに触れ直したいところではあります。